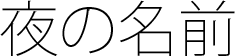
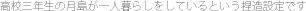
その空間に足を踏み入れると、机に突っ伏した彼女の姿が真っ先に目に飛び込んできた。その途端にふつふつと込み上げる呆れやら言い知れぬ脱力感やらで僕が一瞬胸を詰まらせるのと、彼女を取り巻く周囲の視線が僕を捉えたのはほとんど同時だった。瞬間、その場は耳をふさぎたいほどの歓声にどっと沸き立ち、好奇の視線と野次が四方八方から飛んでくる。
多少なりとも予想と覚悟はしていたが、これほどとは思っていなかった。
この席だけではない。隣のテーブル、さらにはそこらじゅうで耳障りな笑い声がやかましく響いている。鼻腔を刺激する煙草の匂い、耳に届くけたたましい雑音の数々。それらの全部が無性に僕を苛立たせた。たたでさえ電話を受けた先刻からずっと、機嫌は芳しくないというのに。
「ほら、大好きな『月島くん』、来てくれたよ」
彼女の右隣に座る女の人が僕を目で捉えると同時にそう言って、彼女の肩を揺する。ああ、なるほど、と合点がいく。さっき僕に電話をかけてきたのはこの人か。
その様子を眺めていると、今度は別の席から人懐こそうな男が身を乗り出して、僕を不躾極まりなくじろじろと眺めながら口を開いた。
「へー!君がの彼氏?」
「…そうですけど」
応じる声音は自然と低いものとなった。うるさい、黙ってろ。お前には関係ないだろ。気分の悪さに任せ、反射的にそう睨みつけてしまいそうになる衝動を抑える。こいつに限ったことではなく、彼女が日頃付き合っているというこの「サークル」なる集団の中に、ことのほか男が多く見受けられたことがショックだった。その事実は、僕の機嫌をいっそうかき乱す。
好き放題に騒ぎ立て、面白そうにあれこれと声をかけてくる奴らには見向きもせず、僕はすぐにさんの傍に歩み寄る。どんなに無愛想だと思われようが構わない。いくら彼女の友人たちとはいえども、僕はこいつらと仲良くしようなどとは微塵も思っていないのだ。
さんは、僕の近づく気配にも、周りの野次にも気づかずに、両腕に顔を埋めている。ふわふわとした柔らかい髪の間から覗く耳は赤く色づいており、改めてその泥酔ぶりが伺い取れた。
僕はいつものように彼女の名を呼ぼうとして、けれどほんの一瞬だけ逡巡して口を噤んだ。そして、すぐに再び口を開く。
「…」
腰をかがめ、彼女の耳元に顔を寄せて名前を呼ぶ。すると次の瞬間、彼女の周りの女たちが顔を見合わせてやかましく歓声をあげるものだから、僕は思わず顔を顰める。そんな時だった。ようやく顔を上げた彼女のうつろな双眸がのろのろと僕を捉えた。こちらを仰ぎ見るさんの顔は林檎のように赤く上気し、少しばかり充血した瞳は涙でとっぷりと潤んでいる。額には少しばかり汗もかいているようだった。
「……つきしまくん」
さんは少しだけ目を丸くしたあと、そう呟いて、この上なく締まりのない顔で笑う。僕の名前をこれほどまでに甘く形作ることのできる人は他にいないだろう。けれど、そんな甘やかな響きも、見ているこちらの胸が詰まる程とろけたような笑顔も、この場においては全く喜ばしいものではなかった。こんな姿を、僕以外の人間の目に晒すだなんて、そんなこと。
だから、あれほど飲みすぎるなって言ったんだ。
「帰るよ」
「えっ、え?」
何がなんだかわからず、状況の理解もままならぬ様子のさんの手を引いて、彼女の荷物を拾い上げ、僕はすぐにその場を去る準備をする。
「ご迷惑かけてすみません。この人連れて帰るので、失礼します」
心にもない口先ばかりの謝罪と形だけの挨拶を述べ、僕は足早に彼らに背を向けた。背後では再び黄色い悲鳴があがり、「頑張れ」だの「お幸せに」だの、くだらない野次が飛び交っている。彼女はふらつきながらも必死に彼らのほうを振り向いて陽気な声で挨拶をしていたけれど、僕はただの一度も振り返らなかった。苛々する。一刻も早く彼女を連れてこの場から立ち去りたかった。うるさいのも、くだらない馬鹿騒ぎも、大嫌いだ。
さんを家まで運ぶのは、面倒なことこのうえなかった。
別に彼女の身体が重いだとか、物理的な問題というわけではない。とりたてて小柄ではないとはいえ、それでも彼女は僕からすれば小さい身体だ。支えて歩くことはわけもない。それよりも僕を参らせた問題は、酒で陽気になった彼女のその舌が、普段の何倍もよく回りだすことだった。微かに吐息の混じった声で、僕の名を繰り返し呼びながらしがみついてくるものだから、僕はその場でしゃがみこんでしまいたい気持ちを散々持て余した。
僕の腕の回る彼女の背中は少しだけ汗ばんでいる。暦の上ではもう秋とはいえ、夏の名残を残すこの時期の気温は、夜といえどもまだしっとりと暑さを帯びて蒸しているのだ。
鞄から取り出した鍵でドアを開けると、普段から慣れ親しんだゼラニウムのキャンドル―いつか彼女が半ば無理やり置いていったものだ―の香りが鼻をかすめる。今までも僕の家には何度も足を踏み入れている彼女だが、今回訪れるのは約ひと月ぶりのことだった。
僕はさんをすぐにベッドに寝かせて風呂場に向かい、バスタブに湯を張った。彼女から少しでも目を離すことに気は進まないが、目を覚ました彼女はきっと、まず風呂に入りたがるだろうから。
一通り風呂の支度も終えてリビングに戻り、ベッドに横たわる彼女の隣に腰掛ける。なんとなしに軽く頬に触れてみても、身じろぎひとつさえせず、静かに心地よさそうな呼吸を繰り返すのみである。つい先ほど帰宅するまでは、月島くん、月島くん、と何度も繰り返し口にしていたというのに、どうやら彼女はもう既に深い深い眠りの底にいるようだ。その寝顔は、とても年上のそれとは思えないほどにあどけない。僕は気の抜けたような思いで、今一度溜息をこぼした。
(君はのんきなんだよ、まったく)
そう、僕にとって、さんはあまりにものんきすぎるのだ。
さんは僕より一つ年上で、いつもはしゃんと背筋の伸びた、しっかり者と称されるような人だ。
高校時代からよく周りを見て動ける人だったけれど、それでも当時はまだ抜けていて、危なっかしいところが多かった。人を疑うことを知らぬ無邪気さ、こちらの不安をいたずらに煽るような無防備さ。今晩の彼女は、まるで高校当時に戻ったかのようだった。懐かしさを覚える反面、拭えない複雑な気持ちを抱えて、僕は彼女の額に張り付いた前髪をそっと払ってやる。
やがて風呂が沸いたことを告げ知らせる電子メロディが聞こえてくると、僕は自分の寝間着を手に取り、ベッドから腰を上げた。
部活帰りの身体だ。彼女が目を覚ますまでに、せめてシャワーぐらいは浴びておきたかった。
シャワーの水に頭を打たれても、流れ落ちない煙草の匂いに苛立って、僕はいつもよりも荒い手つきで髪にシャンプーを絡めていく。けれど、気を荒げれば荒げるほど、先ほどまでの不愉快極まりない光景が嫌というほど鮮明に脳裏に蘇ってくるのだった。
僕の知らない彼女の居場所。
僕の知らない彼女の友人。
僕の目の届かない彼女の言動。
それらは不安要素となって、しばしば僕の精神を心地悪く揺さぶった。
束縛や嫉妬心なんて、馬鹿馬鹿しく自分には縁遠いものだと思ってきたし、現に今だってその考えには変わりはない。けれど、もう自分をごまかしきれぬほどに胸をかき乱す焦燥感が確かにあることもまた事実だった。
さんは僕と違って、朗らかで、誰にでも分け隔てなく親しみを持って接するような人種だ。高校時代から男女問わず多くの人間に好かれる人だった。そんな彼女に気を持つ男が、いつ大学内に出てきてもおかしくはない。それでも、彼女のコミュニティの外にいる僕は、傍観を強いられるどころか、そもそもそんな男の存在をすぐに察知することさえもできないのだ。それが恐ろしかった。僕の目の届かないところで笑う彼女の姿を想像するだけで、心の均衡などいとも簡単に瓦解した。
言っておくが、彼女は決してやましいことをするような人間ではない。そもそも、できるだけの器量もないだろう。それに、彼女がどれだけ僕にひたむきに好意を向けてくれているかも十分理解しているし、また、僕もそんな彼女の真っ直ぐさを信じている。それでもだ。
僕はいつから、こんなにおかしくなってしまったんだろうか。
長く一つ息を吐くと、先ほどまでの激情がひどく気恥ずかしく、無意味なものに思えてきて、途端にやり場のない虚しさが胸を占めていく。こういう時、己の負の感情を逃がす術を、僕は未だ掴めていなかった。砂嵐のように渦を巻くざらついた感情を持て余してしまう。そんな自らの不器用さが、幾度となく彼女を傷つけてきたこともわかっていた。無論、そんな自分がひどく子供じみていることも、とうに承知の上だ。
そう。嫉妬だけではない。――これは焦りだ。
高校生の僕と、大学生の彼女。僕らを隔てる歳の差は、たかが一年、されど一年だ。僕が今も身を置く烏野高校を飛び出してからの彼女は、目に見えて綺麗になっていく。髪を伸ばし、化粧を覚え、服装だって大人びたものへとシフトした。元々はそれほど派手な顔立ちではないものの、自分を最大限に美しく見せる術を知ったようだった。
女は化けると聞いたことはあったけれど、まさかこれほどとは思いもよらなかった。
未だ自分の感情を制御する術さえ知らない僕と、どんどん前へと進んでいくさん。
今は自分から僕の手を握ってくる彼女が、近い未来、僕の手など離して、振り返りもせず去っていくのではないか。そんな、らしくもない不安に足を取られ続ける僕のひどくみっともない本音など、彼女にはとても言えるはずもなかった。
冷蔵庫から取り出したミネラルウォーターと、コップを二つ持ってリビングに戻ると、先ほどまで丸くなって眠りこけていたさんが既に目を覚ましていた。一度寝たらなかなか目を覚まさない彼女をどう起こすかについて思案し始めていた僕は、いささか面食らってしまう。
「お風呂に入ってたの?」
しかしその声はまだまどろみの中に片足を浸しているようだった。意識はあっても、体勢は先ほどと変わらず寝そべったままだし、瞼も重そうに見える。
「見ればわかるでしょ。ほら次入りなよ、酔っぱらい」
そう言って、よく冷えたペットボトルを彼女の頬に容赦なく押し当てる。すると抵抗することもなく、気持ちよさそうに身を任せたまま、猫のように丸い瞳が僕をじっと見つめるので、なに、と小さく答える。
「月島くんだ」
ほら、まただ。こういう時のさんの声は、彼女が普段から好むような、砂糖のたっぷり入った人工的な飲料と同じ程に甘ったるいのだ。あの種の甘さはどうにも好きになれないが、彼女の声音はどうだろう。こんなにも甘いのに、全く厭らしさがない。そう思ってしまうのは、ひとえに惚れた弱みというものなんだろうか。
僕は、そんな一瞬の心の浮わつきを隠したくて、ふらふらとおぼつかないさんの額を軽く指で弾いた。
「僕しかいないんだから当たり前」
「ふふ」
僕の素っ気ない態度にもめげず、さんは軽やかに笑う。それは同級生の女子のものとはまるで似ても似つかない、鈴のように柔らかく上品な笑い方だ。
「ねえ月島くん」
「なに」
「さっき、って呼んでくれたでしょ」
「……それがなに?」
「初めてだよね」
「はあ?」
さも、何を言っているかわからないといったふうに振る舞うが、そんなものはただの虚勢だ。本当は、彼女がそれを覚えていることに動揺していた。
あの時、いつものように"さん"とは呼ばず、あえて呼び捨てで彼女の名を口にしたのは、咄嗟に湧きあがった僕のくだらない見栄の表れゆえだった。確かに僕は彼女よりも幼い高校生の身だ。それでも、れっきとした彼女の恋人で、歳の差など飛び越えた対等な交際をしているのだということを、あの場で少しでも明確に示しておきたかったのだ。
ああ、もう。あんなにもふやけた顔をしていたくせに、こういうことははっきり覚えているのか。本当に厄介この上ない。
「って。月島くんにそう呼ばれたの初めてだったから、嬉しい」
この人は、僕のプライドや子供のような意地などには全く気付かずに、無邪気に笑っている。
「ほんっとうに、私、月島くんがだいすきなんだよお」
そう言って、僕の腕にぎゅっと抱きついてくる彼女のやわらかい肌に、その甘い言葉に、僕の理性は陥落しそうになるけれど、やはりその声はいつもの彼女のものとは違う。たとえそれが本心だとしても、アルコールに乗せられて発せられた浮薄な言葉など、この状況では素直に喜べるはずもなかった。
「…そんな状態で言われても、ちっとも嬉しくないんだけど」
僕に触れるさんの腕を振り払い、行き場のなくなった彼女の両手を僕はベッドに縫い付けた。シャワーで火照った身体が、いっそう熱さを増していく。さんは目を見開いたまま、驚いた表情で僕を呆然と見上げている。僕よりもずっと小さなその身体は微動だにしない。驚くのも無理はないだろう。僕がこんな乱暴なことをするのは初めてなのだから。
「人の気も知らないで、」
馬鹿みたいだ、こんなの。
子供じみた、ひとりよがりの独占欲に過ぎない。格好悪いにも程がある。そんなことはとうにわかっている。それでも。
「そうやって誰にでもへらへらしてさ」
君が、僕の知らないところで笑っているのがムカつく。
僕に向けるのと同じあの笑顔を、他の奴の前で惜しみなく見せることに、どうしようもなく腹が立つ。
そんな姿を想像して、僕がどんな気持ちになるのか、考えたことあるのかよ。
ねえ。
頼むから、僕をこれ以上揺さぶらないでよ。
⇒